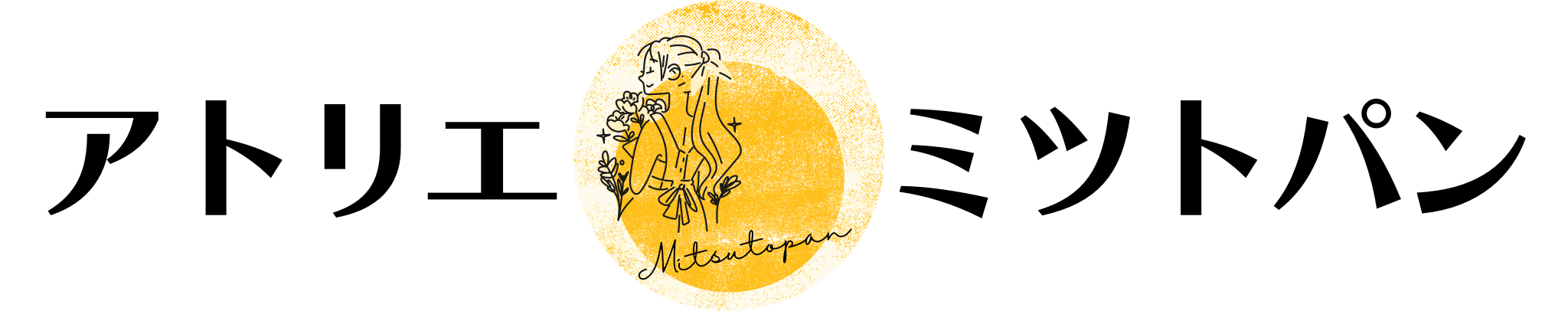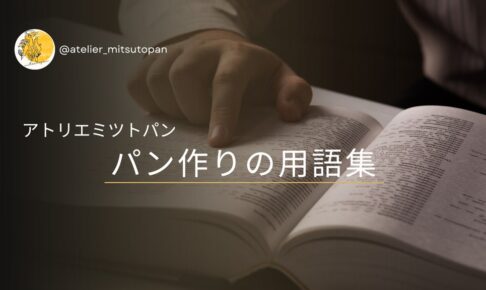オーバーナイト発酵で焼くライ麦入りの田舎パン【パン・ド・カンパーニュ】の作り方。
カンパーニュとは?
フランス生まれの田舎パンです。日本では丸い形にうずまき模様のものをよく見かけるかもしれません。でも本当はもっと幅広く、いろんな形のものがあります。別名は「パン・グランメール」。おばあちゃんのパンという意味だそうです。かつてはパリ近郊の地域の人々が作り、パリに住む人々が買う、という歴史がありました。それぞれの家の自家製酵母でゆっくりと発酵させて作っていたそうですよ。素朴な味わいなのに粉の風味がしっかり活きており、毎日食べても食べ飽きないおいしいパンです。
こちらはほとんどこねないので超簡単。なのにクラストはざくざく、クラムは気泡が散って口溶けがよく、舌触りはもっちり、この食感は病みつきです。
サンドイッチにしても優秀です。素朴なのでどんな具材を合わせても美味しいです。日本ではサンドイッチに生野菜を入れることも多いですが、バゲットやカンパーニュなどの食感を大切にする場合、フランスではあまり生野菜を入れないのだそう。私はドライトマトとサワークリームを合わせるのが大好きです!
ライ麦を全粒粉にかえてもおいしいですよ。
自家製酵母はルヴァンリキッドを使用しています。
■パン・ド・カンパーニュの作り方
■材料
・強力粉 165g(72)
・薄力粉 41g(18)
・ライ麦粉 24g(10)
・ルヴァンリキッド 46g(20)
・塩 4.6g(2)
・水 161g(70)
・はちみつ 4.6g(2)
・インスタントドライイースト 0.9g(–)
*焼成
予熱300℃
生地をオーブンに入れたら5分間まつ
焼成250℃で25〜30分
インスタントドライイーストはサフ赤です。
オーブンの癖等で焼成温度や時間はかなり変わってきますので、それぞれ調整してください。
粉の種類
今回はハード系のパン生地なので、ハードパンを焼くのに最も適している準強力粉を使用します。最近では様々な種類の粉が、割と手に入りやすくなってきているので、可能であれば準強力粉206gをご用意ください。なければ強力粉8:薄力粉2(あるいは7:3)で代用します。
ルヴァンリキッドがない場合
・強力粉 165g(72)
・薄力粉 41g(18)
・ライ麦粉 24g(10)
・塩 4.6g(2)
・水 184g(80)
・はちみつ 4.6g(2)
・インスタントドライイースト 0.9g(–)
イーストの量は変えなくても大丈夫だと思います。少し発酵時間が伸びるかもしれませんが。心配な方は1gまで増やしてみてください。
■作り方
タイムテーブル
計量(5分)
↓
ミキシング(3分)
↓
予備発酵 / 一次発酵(30分)
↓
折りたたみ1回目(3分)
↓
予備発酵 / 一次発酵(30分)
↓
折りたたみ2回目(3分)
↓
予備発酵 / 一次発酵(30分)
↓
折りたたみ3回目(3分)
↓
オーバーナイト発酵
↓
復温
↓
成形(5分)
↓
最終発酵 / 2次発酵
↓
仕上げ(10分)
↓
焼成(30分)
時間はあくまでも目安です。要所、要所で、生地の温度や質感を見極めてください。ベテランさんはもっと短時間に効率よく仕上げられるかもしれません。生地の様子を見極めるポイントは、下記で示していますので、参考になさってください。
■工程
下準備
イースト液を準備します

水、はちみつ、インスタントドライイーストを合わせて、イースト液を作ります。
水温
生地によりますが、水分の温度は25〜35℃(夏場の室温が高すぎる場合は冷水、冬場の室温が極端に低い場合や機械でこねる場合は40℃強まで)の範囲で調整します。*15℃以下の冷水を使用する場合はインスタントドライイーストは粉類の方に混ぜてあげてくださいね。
1

粉、塩、ルヴァンリキッドの入ったボウルにイースト液を注いで、軽く混ぜます。こね台に出して10回ほどやさしくこね、生地をまとめます。
塩
いつもは後入れする塩ですが、今回ははじめに入れてしまいます。あまりこねたくない生地なので、後入れでこねすぎになるのを避けたいのでそうしています。
こねあげ温度
23℃

油脂を塗ったボウルに生地を入れて予備発酵させます。
2

発酵中、30分に1回、生地を上下、左右に1回ずつ折りたたみます。計90分、3回、折りたたみます。
生地を傷めないために
指先を水で濡らして作業してください。
3

3回目の折りたたみのあと、生地を平たい容器に広げてラップを密着させて、オーバーナイト発酵させます。
オーバーナイト発酵
オーバーナイト発酵(低温長時間発酵)は、やり方は様々ですが、多くは10〜18℃くらいで、10時間保存、24時間保存、というように指南されている講師さんや書籍が多いかと思います。これって家庭ではかなり難しいです。ですから家庭で行うオーバーナイト発酵は、冷蔵庫の野菜室5〜8℃を使用します。4℃以下の冷蔵庫内ですと酵母は働けないので、野菜室に入れる訳です。
野菜室ではなく普通の冷蔵庫内で熟成させることもありだとは思います。この場合はもっと時間がかかりますし、いくつかの工夫が必要です(イーストを増やしたり、復温時間を長めに取ったりなどなど)。
発酵速度というか、勢いというかは、生地保存中の温度や湿度の他、生地に加えるイーストの量や加水量、糖分、酸素の量や生地の酸度などでも変わってきます。それらを工夫すれば、発酵速度はある程度コントロールすることが可能です。これらをコントロールして、最も好みのやり方を探すトライアンドエラーが、オーバーナイト発酵と付き合っていくためには必要かもしれません。
4

生地をこね台に出して、やさしく広げ、復温させます。
復温
生地を室温近くに戻しながら、ゆるやかに酵母を活性化させてあげることです。温度が上がっていくのと、新しい酸素が供給されるので、この間も発酵は進みます。冷たすぎると生地は伸びが悪かったりして傷みやすいので、軽く緩めてあげる意味もあると思います。
15℃前後を目安にしていますが、冷蔵庫での発酵が思うように進まなかった場合は、ここで時間調整をすることができます。膨らみが悪ければ長めに、2倍近くまで膨らんでいれば、過発酵になってしまうのですぐに次の工程に入ります。
5

生地の形を丸く整え、バヌトン(発酵カゴ)に入れて30分ほど発酵させます。
バヌトン(発酵カゴ)
発酵カゴを使う場合は、綴じ目は上です。粉をしっかりふってください。
6

発酵カゴをひっくり返して生地を取り出します。焼成の直前に生地表面にクープを入れます。
7
生地全体とオーブン庫内に水を霧吹きし、焼成します。

■ポイントとコツ
オーバーナイト法の生地
冷蔵庫から出したての生地はきちんと発酵していても冷たいままです。そのまま乾燥を防ぎながら、10℃〜15℃にまで生地温度が戻って、さらに生地が期待する大きさに膨らんでくるのを待ちます。これが復温です。
このとき、発酵に利用した容器のまま復温させる場合は、生地の見極めがしやすいです。温度は測ってチェックできますし、大きさは膨らみを目視できます。ただ、この場合、容器が冷たいままですし、生地も広がっていないので時間がかかるとともに、生地の発酵状態にムラが出やすいです。
慣れてきたら、生地をこね台に出して復温させてみてください。優しくパンチを入れて新しい呼吸を促してあげるとともに、そのまま乾燥を防ぎながら10℃〜15℃にまで生地温度が戻って、また全体的にふっくらとしてくるのを待ちます。発酵倍率を確認しにくいんですが、何度か作って慣れてみてください。
オーバーナイト発酵で生地がうまく膨らまない場合
冷蔵庫内の温度が低すぎたり、予備発酵(一次発酵・フロアタイム)が短すぎたりして、生地が充分に膨らんでいなかった場合は、この復温の工程で発酵具合を調節します。
復温時間は室温にもよりますが、1〜2時間ほどかかることもあります。だから早めに生地を冷蔵庫から出して、その間は別の家事を……というように、ご自身の日常生活のもろもろのお仕事と平行でパン作りを行うのがベストです。
オーバーナイト法の利点は、ある程度の「ほったらかし」が許されるところです。
ルヴァンリキッドって何?
詳しくはこちら「ライ麦ルヴァンリキッドの起こし方」をご覧ください。
「Levain」ルヴァンというのはフランス語で発酵種、酵母のこと。主にライ麦などの野生酵母を育てて、リキッドや元種として、パンを焼くのに利用するものです。
バゲットやフォカッチャのように副材料の少ないリーンな生地の場合は、今回のように発酵種を加えたり、低温長時間発酵で小麦の芳香を深めてあげることで、生地が生まれ変わったようにおいしくなります。お試しください。
カンパーニュのこね方
こね方って色々あるので、数ある中のひとつとしてご覧ください。
粉の風味を深く感じたい生地の場合はあまりこねません。こちらのカンパーニュはまさにそんな生地です。このレシピではさらに発酵種(ルヴァンリキッド)で複雑な風味を追加して、生地の旨味を味わいます。できるだけ触りたくない生地なのですが、仕上がるパンの香りと内層の口どけのために軽く生地を鍛える作業を入れています。この口どけはリーンな生地の美味しさの第二のポイントです。グルテンをより柔軟にして、香りをたくさん閉じ込めてあげることができる生地を作る一方で、ほどほどに切れやすい強化にとどめて、焼成時にまばらにグルテンが壊れる生地を作ります。この作業で生地に気泡が入り、焼き上がりの内層が、気泡ポコポコの軽い口どけのものになるのですね。
折りたたみ作業のやり方はたくさんあります。これは一例です。英語圏のレシピサイトを漁って見つけてきました。「トラディショナルなやり方」として紹介されていました。生地の真ん中を引っ張り上げて、下にたたんでいくやり方です。逆でもまったく問題ありません。生地の上下(あるいは左右)をやさしく伸ばして上にたたんでいく方法ですね。他にも生地を作る初期の段階で、生地を薄ーく伸ばしてたたんでいく方法(ラミネーション)なんかもあります。いずれの場合も、お水をたっぷり使ってあげてください。くりかえしの折りたたみ作業でも生地が傷みません。
家庭のオーブンでのバゲット生地の焼成について
家庭のコンベクションオーブンでクープを開かせるのは難しいですよね……。私は銅板や小石は使っていないので、一応、どなたでもすぐにできる工夫だけ書き留めておきます。オーブンは最高温度で予熱してください(私のオーブンは300℃です)。ここではプラスアルファでできる工夫を記しています。基本的には250℃で25〜30分焼成することでパンは美味しく仕上がります。
1
オーブン庫内の上段と下段の両方に天板を入れて、庫内の底面にバットを置いて予熱する(下の天板は逆向き・そこにオーブンシートごと生地をのせる)
2
予熱完了後、手早く天板に生地を移したら霧吹きで生地を湿らせる(水蒸気がたくさんあがるので火傷に注意してください)
3
庫内のバットに熱湯を(100cc強ほど)注ぎ、庫内にも満遍なく霧吹きをしてから、生地を庫内へ
4
そのまま庫内で5分放置してから焼成スタート
5
250℃で20分の焼成が終わったら、上段の天板を取り出し、下段の天板の前後を(生地の手前と奥を)入れ替えてから、5〜10分焼成する
オーブンご家庭のオーブンの癖に合わせて温度や時間を調整してください


■材料と道具
ここでは私が実際に使用している材料や道具、おすすめなんかをご紹介します。リンクが見つかるものは貼っておきますね。ご参考になさってください。
材料
強力粉
よく使う国産小麦は「キタノカオリ」。カナダ産は「スーパーノヴァ」。強力粉はほとんどこのうちのどちらかです。特にキタノカオリは大好きな小麦です。
その他の粉
薄力粉はドルチェ。安定して手に入るので使い勝手がいいです。ライ麦全粒粉は北海道産のものを使用しています。
インスタントドライイースト
最近ドライイーストとかイーストとか言わないように気をつけようと心に決めました(笑)。インスタントドライイーストは、サフ赤を使用しています。
こちらは冷凍して保存しています。特に凍って固まったりしないので、そのまま必要量だけすくいだして使います。
道具
ボウルと計量カップ
こねるときはガラスボウル。発酵の具合も全方向から確かめられます。経年劣化の濁りみたいなものも出にくいと思うので、長く使えるのではないでしょうか。
私はiwakiのガラスボウルを使用しています。本当はHarioも気になっているけど……。
この頃の計量カップはHarioです。今は無印良品。いずれもガラス製で品の良い感じでメモリが付いているのでお気に入り。それにやっぱりガラスの手触りが好きです。
野田琺瑯のバット
オーバーナイト発酵で使用しているのは野田琺瑯のバット(アイボリー)です。ホワイトシリーズよりも好きです。温かみがありますよ。
よく使用しているサイズは21枚取りです。他にキャビネサイズと15枚取りを愛用しています。キャビネサイズのリンクが見つかりません。探しておきますね。
スケール
パン作りに欠かせないのはスケール。3kgまで、0.1g単位で計ることができるものをおすすめします。私が使用しているのはタニタのスケールです。
バヌトン(発酵カゴ)
これは馬嶋屋さんで購入したんだっけ、浅井商店さんだったっけ?と曖昧ですが、とっても便利なプラスチック製です。お手入れ楽ちん。
ただ、発酵をとるものはバヌトンでなくてもいいです。ボウルにパンマットを敷いて代用してもいいと思います。お好みのもので作ってください。クッペ型に整えてパンマットで発酵させたってできますし。このとき、粉をたっぷりとふることだけは守ってください。動画でもたっぷりふっています。