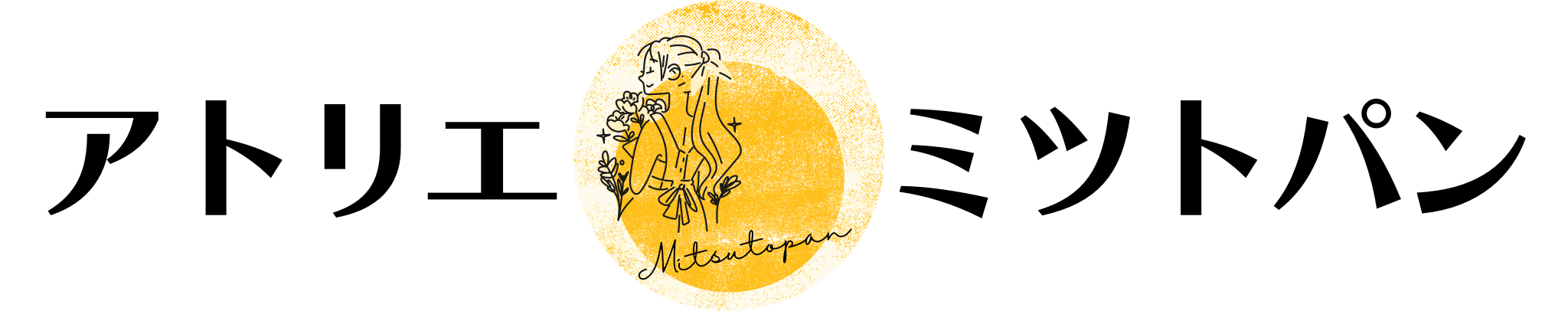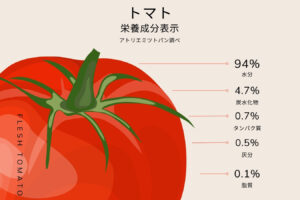■YouTube
アルカリ性の水溶液、ラウゲン液に浸してから焼き上げるドイツの食事パンです。

ハートみたいな独特の形と艶のある焼き色に特徴があります。語源はラテン語の「腕」。この独特の形は愛を表しているというロマンチックな説もあるのですが、はっきりとした謂れはわかっていません。今日のドイツではパン屋さんのシンボルマークにもなっています。ドイツを代表するパンなんですね。
今回、こちらでご紹介するのは一次発酵なしのお手軽プレッツェル。本場でも発酵は短めで、その代わり酵母を少し多めに配合するのが一般的みたいです(知人談🧐)。
プレッツェルと言ったらこの独特の成形とラウゲン液に浸すことで得られる色と艶。
この形は一見、複雑に見えるけれど、作ってみると意外とそうでもなくて楽しいです。
アルカリ性の溶液(ラウゲン液)は、本場では水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)を溶かしたものを使用するのだそうですが、劇薬なので、家庭にある重曹で代用します。色は少し薄くなるような気もしますが、重曹でも大丈夫!! 艶っぽくてきれいな色が出ます。
ちなみにドイツ語の綴りは「Brezel」ブレゼル、ブレッツェルですね。「Pretzel」は英語圏から来たの呼び名なんでしょうか。プレッツェルか、ブレゼルか。どちらで呼ぶかまだ答えが出ないので、ここでは馴染みのある「プレッツェル」と呼びますね。
■ラウゲンプレッツェルの作り方
■配合
4個分

▶︎パン生地
・強力粉 105g(70%)
・薄力粉 45g(30%)
・水 45g(30%)
・牛乳 45g(30%)
・練乳 7.5g(5%)
・はちみつ 3g(2%)
・インスタントドライイースト 0.6g(–)
・塩 2.7g(1.8%)
・ラード(ショートニング) 15g(10%)
▶︎ラウゲン液
・お湯 1500ml
・重曹 50g
■フロー
◆生地を作る
捏ねあげ温度
25-27℃
分割
4分割
一次発酵にベンチタイムを含む
25℃ / 10-20分
成形
プレッツェル成形 / 要所要所で10分程度休ませながら
最終発酵
温度28-30℃ / 40分
◆焼成する
予熱250℃
焼成230℃で12〜15分
フローは目安です。生地の状態を見極めながら、各工程を調整してください。焼成温度はお持ちのオーブンに合わせて調整してください。
下準備
イースト液の準備をします

水、牛乳、はちみつ、インスタントドライイーストを合わせてよく混ぜます。
生地によりますが、水分の温度は15〜35℃(夏場の室温が高すぎる場合は低め、冬場の室温が極端に低い場合は高め)の範囲で調整します。ただし、最も優先されるべきなのは捏ねあげ温度です。捏ねあげ温度が25-27℃におさまる範囲で調整してください。
やむをえず15℃以下の冷水を使用する場合は、分量内の水を一部取り分けて25-30℃くらいにして、インスタントドライイーストだけ溶かしてあげてください。
粉類の準備をします

強力粉と薄力粉、塩を合わせておきます。
1

粉類にイースト液を加え、ひとかたまりになるまで混ぜます。

粉っぽさがなくなるまで混ぜたら、生地を30分ほど休ませます。
2

こね台に出してこねます。

こねの後半になったら、生地の表面を荒らさないように気をつけます。生地を何度も畳むようにしてこねると荒れにくいと思います。
緩やかに生地の表面がつるんと整ってきます。
3

ラードを加えてこねます。

油脂をグルテンの隙間に均等に入れこむのには少し時間がかかります。
繋がってきたグルテンはちぎると傷んでしまうので、無理に伸ばしすぎてちぎったりしないように心がけます。その際、生地をある程度細かく切って揉み込むと油脂が入りやすいです。
可塑性のある油脂も、液体油脂も同様です。液体油脂の方が少し入りにくいですが、10%未満の配合量で手ごねの場合はきちんと入りますので(今回はギリギリ10%ですが)、丁寧に揉みこんで吸収させてあげてください。
生地が油脂を満遍なく吸って、はじめツルツルして台離れの良かった状態から、再びしっとりと手のひらやこね台にはりつくような感触になったら、こねあがりです。

こねあげ温度
25〜27℃

私もよくバターを使います☺︎
4


4分割して、丸め直します。その後、生地を10-20分、休ませます(ベンチタイム)。
ここから生地を休ませながら成形していくので、ベンチタイムは短めです。
生地は休ませると緩みます。緩むと伸ばしやすくなる(構造緩和)、逆にいじると締まって(加工硬化)伸ばしにくくなる。なのでここからインターバルを挟んで生地を伸ばしやすくしながら成形していくのです。
もちろんこの間も発酵は進みます。発酵が進みすぎると、生地表層が荒れやすく、生地切れしやすくもなるので、作業は手早く行うのがポイントです☺︎
5

成形します。

65〜70gの生地を、真ん中だけ膨らんだ棒状に伸ばします。
1段階目

生地は4つあるので、4つの生地を一通り1段階目まで伸ばしたら2段階目へ、4つの生地を一通り2段階目まで伸ばしたら3段階目へ、というように進めていくと、生地の傷みも癒されて伸ばしやすくなると思うので、やってみてください。
2段階目

3段階目

3段階目まで伸ばしたら、プレッツェルの形に成形していきます。

6
最終発酵させます。ひと回りふっくらする程度で大丈夫です。
最終発酵
温度28〜30℃ / 目安40分
7

ひとつひとつ、ラウゲン液にくぐらせます。15〜30秒を目安に引き上げます。
水を軽くグラグラする程度に沸かしたら、重曹を静かにいれます。良く溶かして、生地をくぐらせます。
重曹を溶かす際には火傷や吹きこぼれにご注意ください。動画の通りです。動画を観ていただければ、私がいかに大雑把かわかってもらえると思います💦
みなさんはもっと静かにやりましょう!
8


仕上げに、クープを引いて、岩塩を散らします。
9
焼成します。

■ラウゲン・プレッツェル
ラウゲン・プレッツェルとは?
アルカリ性の水溶液、ラウゲン液に浸してから焼き上げるドイツの食事パンです。ハート型みたいな独特の形と艶のある焼き色に特徴があります。語源はラテン語の「腕」。
この独特の形が何を指すのか、謂れは山ほどあってはっきりとしていません。例えば、罪を犯したパン職人が恩赦のために作ったとか、パン屋さんの腕組みの形だとか、修道士が祈りを捧げる際の腕の形だとか、あるいは「ハート型は愛を表しているのだ!」というかなりロマンチックな説もあるみたい。

そもそも起源についても謎なのですって。プレッツェルはドイツではなくフランスのアルザス地方の生まれだという説もあるみたいです。またまたアルザスか、という感じですね。アルザス地方は本当においしいものの宝庫です。
ただ、プレッツェルはドイツのパン屋さんのシンボルマークにもなっています。発祥がどうであれ、今ではドイツを代表するパンになっていることは間違いないですね。
もうひとつの特徴、ラウゲン液ですが、ご家庭では重曹で充分だと思います。色も艶もきれいに出ます。ちょっとだけ薄めですが。
このラウゲン液の発想が生まれた説はかなり可愛くて気に入っています。パン屋さんで、猫がパン生地にぶつかって、いくつかの生地を苛性ソーダ液の中に落としてしまったのだそうです。もったいないのでそのまま焼いたら美味しかった、という笑。思えばパンはいくつもの偶然に誘われて今日まで進化してきたのですねー。宇宙を感じます。
この苛性ソーダのコーティングはパンを日保ちさせることにも役立っています。でもいつまでもずっとカリカリというわけではないので、せっかくご家庭で焼くなら、焼き立て(冷めたてのことです)を食べて欲しいです。本当に!おいしいです。
ラウゲン液のケトリング(そもそもケトリングではないんですが)の温度についてはいろんな見解があって、私はベーグルのように(軽く沸いたお湯で)行っていますが、本来は煮る必要がないみたい。ただ、完全に冷めた重曹液でやってみたら、うまく色づきませんでした。ご参考までに。
食べ方
本場ドイツでは、ふりかけられた岩塩を好みの塩分になるように落として食べるのだそうです。あとは無塩バターやヌテラなんかをサンドして食べるのもおいしいみたい。
「え、サンド?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。プレッツェルは水平にスライスしてサンドイッチにもできるんですよ。

ドイツの方に「そんな食べ方がおすすめだよ」と言われることから分かる通り、ドイツでは(様々なプレッツェルがあるようですが)全体的にもっとふっくらしてソフトなものが主流みたいですね。
一方、アメリカではプレッツェルと言えばカリカリ固いもので、ドイツのプレッツェルは「Soft Pretzel」と呼ばれています。
私は、焼き立てには無塩バターを挟んでそのままもりもり食べるのをおすすめします。リベイクするなら、無塩バターとカリカリベーコンがおすすめ!!おいしいです!!
成形
今回ご紹介しているのは、カリカリとさっくりを両方楽しめるレシピです。腕の部分の細いところはカリカリ、太い部分はさっくりを目指します。

今回は70〜80cmに伸ばしましたが、もう少し伸ばしてあげるともっとメリハリがついておいしいです。こね台と撮影範囲(と技術)の関係でこれ以上は伸ばせないのですが、もし広いキッチン台をお持ちの場合はぜひトライしてみてください!
生地作り
牛乳を入れるかどうかはかなり迷ったのですが、クラムの少ない生地だからこそ、ミルク風味とか香りって大事かもしれないな、と思って配合しています。バターを入れないのでなおのこと。
あとは細かいことなんですが、色づきの良さやネジネジの形がきれいにくっきりと出て残ることにも一役買っています。一方で伸びにくい生地になるので、加水全量を牛乳に置き換えるのは難しいです。加水量を増やしてもだめでした。牛乳の分量を加水の半分の量におさえるこのレシピでも生地の伸びが物足りないので、練乳を入れています。油脂も多めに入れています。
油脂については、伝統的なプレッツェルではラードを使用するようです。ドイツはラードを使うお菓子も有名ですよね。おそらく旨味というよりは食感のショートニング性を狙っているんだと思うので、ショートニングでも大丈夫だと思います。もっと言えば、バターでもおいしいです。香りがよくなるので。ご家庭にあるものをご使用ください。配合量は試行錯誤してくださいね。

■食材
強力粉
スーパーノヴァを使用しています。一般的な最強力粉のように添加物も入っていませんし、非常に使いやすいです。国産はよくキタノカオリを使用していますが、吸水の感じも似ているので、私はこの二種をよく使用します。
薄力粉
ドルチェを使用しています。いつでも安定的に手に入り、普通においしいです。
インスタントドライイースト
サフ赤です。いつもこれ。
冷凍できます。凍ったりしないので、冷凍の状態のまますくいだして使用しています。
ラード
ラードはリンクが見つからないので、愛用しているショートニングを載せておきますね。トランス脂肪酸フリーのものです。
■道具
ボウル
パン作りはガラスボウル。発酵の具合も全方向から確かめられます。経年劣化の濁りみたいなものも出にくいと思うので、長く使えるのではないでしょうか。私はiwakiのガラスボウルを使用しています。
すくいざる
ベーグルはあく取りでもすくえるのですが、プレッツェルはもっと大きくて繊細なのでこちらのサイズが便利です。
クープ
クープは最近はこのカミソリをこのまま持って使用しています。プレッツェルはハサミで切るのもいいですね。
スケール
パン作りに欠かせないのはスケール。3kgまで、0.1g単位で計ることができるものをおすすめします。私が使用しているのはタニタのスケールです。